|
1998.12.9刊/ベースボール・マガジン社/落合博満・著 |
|||
 |
全四章にわたる落合の集大成、
CDでいえば『ベスト盤』とでもいうべき書である。
第1章『落合は引退しない』では引退にいたる決意、
現在の心境を語り、
第2章『落合博満・十番勝負』では過去の名場面を振り返る。
かつての名シーンが脳裏に甦り、
当時を知るオールド・ファンにはたまらない一章だ。
そして第3章『監督・落合、理想のチーム』では、将来、
いつか自分がもし監督になったとき、
どのようなチーム作りをしようか、落合の「夢」が描かれている。
第4章『21世紀の野球選手へ』では
プロ野球が現状抱える問題点と、それに対する提言を。
本書では過去・現在・未来における「落合イズム」が凝縮されている。
「元締めは何冊も書を出してますが、どれか一冊買うとすれば、どれですか?」
と聞かれれば、私は文句なくこの書を薦めるだろう。 | ||
|
落合は、野球の試合に“ストーリー”があると考えている。
「こういう流れだから、きっとこうなるはず」。 そこには論理的な根拠など、ない。 理由があるとすれば、「その方がストーリーとして面白いから」だ。 音が放ったノーヒットノーラン阻止の1ヒットは、いわば、 “偶然のための必然” なのである。
「こういう流れだから、きっとこうなるはず」。
私が野球を観るのも、野球を単なる技術の競い合いではなく、
「ストーリー」であると考えるからだ。
 「ストーリー性のある野球」。 それとは対極に位置する野球を目指したのが、 読売・ナガシマ終身名誉監督だ。 ナガシマは“常勝・読売”を必然にしようと画策し、 一切の偶然性を排除しようと、他球団のエースや4番を奪い獲り、 「読売のチーム力をあげるだけでは飽き足らず、 ライバル・チームの戦力を削る」作戦で、 「間違いなく勝てる戦力」を整えた、はずだった。 (個々の成長・レベルアップを妨げるこの方針は、 日本のプロ野球の発展を10年遅らせた。 その意味でナガシマはプロ野球界の癌であり、大罪人である。) だがしかし、彼は「常勝チーム」を作ることは出来なかった。
頼みの4番が原因不明のスランプに陥ったり、
頼みのエースが突然の故障でローテが頭から狂ったりしたことが、
目に見える「原因」である。
水戸黄門が、カネと権力で悪代官を屈服させたとして、観衆は喜ぶだろうか?
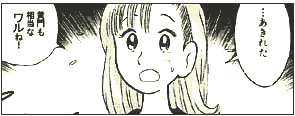 野球人気が落ち始めたのは、読売がカネによる補強に走ってから、と言われる。 2000年の読売の独走Vのときは、勝てば勝つほど読売戦の視聴率はうなぎ下がりに落ち、 氏家日本テレビ会長は、 「読売が強すぎると、お客さんが安心してテレビのチャンネルを替えてしまうんですな! 強すぎるのも困りもんですわ!」と アンポンタンな分析 をしたものだが、案の上、 読売が優勝しても世の中の景気は悪くなる一方で、 1点差の接戦の試合をしていても、読売戦の視聴率があがる事はなかった。
| |||